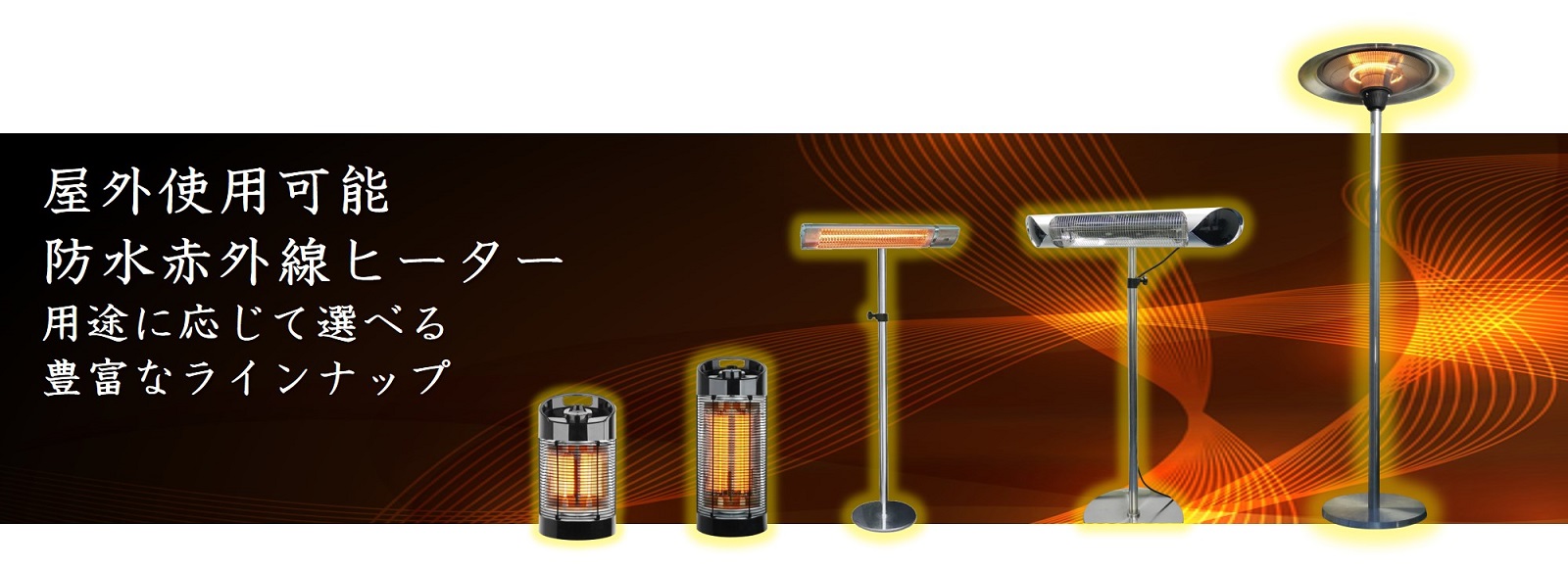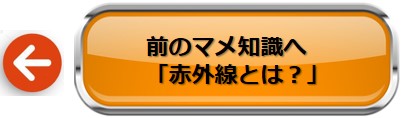遠赤外線・近赤外線、結局どっちが良いの?
前回の【マメ知識①】で、赤外線には遠赤外線・近赤外線、そして中赤外線がある、という説明をしました。また、少しだけですが、ヒーターの種類によって遠赤外線を放射するものや、近赤外線を放射するものなどがある、という説明もしました。
では結局のところ、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターでは、どちらが良いのでしょうか?
今回は、もう少しこれらの違いを掘り下げてみたいと思います。
まずは、下の比較表をご覧ください。
|
項目
|
遠赤外線ヒーター
|
近赤外線ヒーター
|
備考
|
|
ヒーターエレメント(素子)の発熱温度
|
600 ~ 900℃
|
2,000 ~ 3,000℃
|
温度が高いほど、後述する電気からのエネルギー変換効率や、まぶしさが増加します。
|
|
電気⇒放射熱 へ変換するエネルギー変換効率
|
約 60 ~ 70%
|
約 90%
|
|
|
人体への熱吸収率
(暖房効果) |
約 60 ~ 70%
|
約 30 ~ 40%
|
近赤外線は、金属への熱吸収率が優れている
|
|
可視光量
|
少ない
(まぶしくない)
|
多い
(まぶしい)
|
|
|
電源投入から発熱するまでの起動時間
|
約 10 ~ 60 秒
|
約 1 秒
|
|
|
電源投入時の突入電流
|
小さい
|
大きい
(ブレーカが上がる可能性がある)
|
多くの近赤外線ヒーターの素子で使用されているタングステンは、常温では抵抗値が低いため突入電流が大きくなる傾向があります。
そのため、小容量のヒーターをご使用して頂いた方が良い場合があります。 |
|
加熱バラツキ
|
小さい
|
少しある
|
近赤外線は黒色に近い部分に熱が集中する傾向があります。
|
|
用途
|
数十分~数時間の暖房時間で、広めの局所暖房
↓ テラス席など |
数分~数十分程度の短時間で、狭い範囲の局所暖房
↓ トイレなど |
|
いかがでしょうか?
近赤外線では、電気からのエネルギー変換効率としては 約90%と高い効率なのですが、人体への熱吸収率は低く、同じ量の電気エネルギーとした場合、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターは、暖房効率としては、最終的には同程度ということになります。
但し、近赤外線は、まぶしさの問題や突入電流の懸念より、小容量のものとなる傾向があります。この特性と、起動時間が非常に速いという点から、当社ではトイレなどでの特に限られたスペースでの局所暖房として検討いただくことをお勧めします。
対して遠赤外線は、近赤外線よりも優れた暖房効果であることなどから、局所暖房 全般的にご利用いただけます。
お客様の用途に応じて、ヒーターを選択する、ということになりますが、その際にはぜひこのサイトを参考にしてください。
屋外で使えるChrester(クレスター)の防水 赤外線ヒーターは、近赤外線・遠赤外線それぞれをラインナップし、用途に応じて選べるようになっています。ご興味ございましたら、下記リンクよりご覧くださいませ。